土曜プログラム 2分野 音のない世界をのぞいてみよう他
- 土曜プログラム
- 土曜プログラム

10月18日(土)第5回 土曜プログラムが行われました。
今回は、第2分野から2つの講座をご紹介しましょう。
全180以上の講座から、生徒たちは自分の興味関心をもとに講座を選びます。
自分で時間割を作る、それが土曜プログラムの日です。
興味のある人たちが集まった異学年のクラス編成なので、普段の授業とは少し趣きのことなった体験や経験ができます。
「音のない世界をのぞいてみよう」では、聾(ろう)の方と手話通訳の方を講師に招き、通年8回で手話や音のない世界を学びます。今年の受講生は14人。少人数だからこそのあたたかい雰囲気です。実は、講師たちは親子です。
これまでの授業では、生徒は自分の学校名や名前、生まれた日、出身の都道府県の言い方(表し方)などをならいました。色のさまざまや、重い・軽い、すばらしい、おいしいなど様々な形容詞も知ることができました。
今日は、都道府県の言い方をおさらいし、さらに文章を作るやり方でブラッシュアップしました。

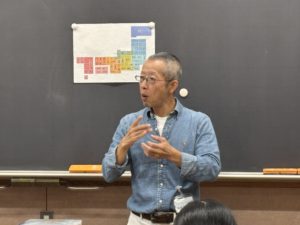
北海道から九州、沖縄まで。地図を目の前にしながら講座はすすみます。
都道府県名を手話で伝えることができるだけでなく、
「〇〇県に行きたいです。なぜなら〇〇をしたいから」のような理由もつけた言い表し方を体得しました。
県名を教わるときも、先生方の知識とユーモアがさえています。
例えば鳥取県の場合、「スターバックスコーヒーが(日本で)最後にできたところです。」など。
「スターバックス」を手話で表す表現ももちろん会得しました!(あの女の人のウェーブのかかった髪の毛の形を両手で表します)

新潟県は、佐渡島からきている手話表現、
滋賀県は、楽器の「琵琶」からきている表現、
大阪と横浜は、形は似ているものの、手の位置が、頭の上か下かで変わるなど
細かな表現方法をたくさん教わりました。生徒たちはあっという間に覚えていきます。


「鹿児島に行きたい。(なぜなら)桜島をみたいから。」
のような表現や、「北海道の札幌に行きたい。そこで札幌ラーメンを食べてみたいから」など個々の表現を詳しく習い、生徒たちの眼が輝いていました。飛行機で行くのか、列車などでいくのか、によっても手話表現が変わります。
自分の言いたいことを、口(音声)でも手話でも表現できたら「ことば」の世界がうんと広がります。手話は目に見える言語なのです。来月からデフリンピックも来月始まります。1ヶ月を切りました。
きっと生徒達は、家でもたくさん手話表現を家族に教えてくれることと思います。音のない世界がもっともっと広く世の中に広まるといいですね。
また、音楽療法を知る講座もありました。
音楽療法士となっている卒業生が講師です。
講師がトーンチャイムや鳴子なども持ってきてくれました。生徒が実際に楽器を動かして音を出しました。障がいをもった子どもの療育や、介護の現場、病院でのケア、自宅での療養、手術中に流す音楽としてなど、音楽は様々な場面で用いられています。「落ちこんだときにはどんな音楽を流すか」、(または無音派か)など生徒に問いかけて意見を共有する場面もありました。
生徒たちは「音楽と治療がこんなに密接にかかわっているなんて知らなかった」と感想をもらし、音楽と治療の関係に目のひらかれた様子でした。
いろいろな講座を受講して自分の世界を広げられるのが、土曜プログラムの特長です。
今後もお楽しみに。
(担当 二井)